
税理士になるための会計大学院はどこがいいか迷っているあなたは、税理士資格取得に向けて真剣に情報収集されていることでしょう。会計大学院への進学は、税理士試験の科目免除制度を活用し、効率的に資格取得を目指す上で非常に有効な選択肢です。しかし、数ある大学院の中から、自身の学習スタイルやキャリア目標に最適な場所を見つけるのは容易ではありません。
この記事では、会計大学院の選び方から、各大学院の具体的な特徴、進学のメリット・デメリット、さらには入学後の学習やキャリア展望まで、あなたが知りたい情報を網羅的に解説します。この記事を読めば、あなたの疑問が解消され、最適な一歩を踏み出すための具体的な道筋が見えてくるはずです。
- 会計大学院に進学するメリットとデメリットがわかる
- 税理士科目免除制度の仕組みと活用法が理解できる
- 主要な会計大学院の学習環境と特徴を知ることができる
- 大学院選びの具体的な基準と注意点がわかる
もくじ
会計大学院はどこがいい?税理士志望のおすすめ大学院

- 税理士を目指す方におすすめの会計大学院
- 税理士試験の科目免除制度の概要
- 大学院進学のメリット:
- 大学院進学のデメリット
- 税理士科目免除が可能な大学院の評価基準
- オンラインや夜間の対応状況
税理士を目指す方におすすめの会計大学院
税理士になるために会計大学院を選ぶ最大の利点は、税理士試験の科目免除制度を利用できることです。税理士試験は通常11科目中5科目に合格する必要がありますが、会計大学院で税法や会計分野に関する修士論文を提出し、所定の単位を取得すると、特定の科目が免除されます。具体的には、税法に関する論文であれば税法2科目、会計学に関する論文であれば会計学1科目の免除が認められます。
この科目免除は、専門知識を深めながら試験準備の負担を軽減できるという大きなメリットがあります。特に社会人や既に実務に携わっている方にとっては、体系的に専門知識を学ぶ貴重な機会となるでしょう。ただし、科目免除を受けるには、国税庁が定めた基準を満たす大学院を選び、修士論文が審査を通過する必要があります。そのため、税法や会計学を専門とする教授が複数在籍し、多角的な研究支援体制が整っている大学院を選ぶことが重要です。
税理士試験の科目免除に強みを持つ大学院をいくつかご紹介します。
LEC東京リーガルマインド大学院大学
LEC会計大学院は、350名以上の税理士科目免除認定者を輩出している実績があります。資格試験の総合スクールであるLECが母体となっており、以下の特徴があります。
- オンライン完結:全コースがオンラインで完結できるため、日本全国や海外在住の社会人でも学びやすい環境です。
- 社会人向けカリキュラム:学生の平均年齢は38.7歳で、9割以上が現職を持つ社会人です。忙しい社会人でも学習しやすいよう、土日をメインとしたスケジュールが組まれています。
- 戦略的な修士論文指導体制:免除認定にふさわしい質の高い論文作成を支援するため、毎週繰り返される草稿提出と指導のサイクル、主査教授に加えて構成指導・文章指導担当教員が加わるチーム制での指導が行われます。
- アカデミックライティング:論文執筆のための基礎スキルを習得するための正規科目「アカデミック・ライティング」が用意されています。
大原大学院大学会計専門職大学院
大原大学院大学は、高度な会計専門職業人の養成を目指しており、税理士の科目免除に対応しています。
- 資格対策講座の全面的なバックアップ:大原学園の資格対策講座を課外学習として無料で受講できるため、資格取得のサポートが充実しています。
- 都心立地と柔軟な学習環境:キャンパスが都心にあり利便性が高く、昼夜開講制を採用しているため、仕事をしながら学ぶ社会人にも適しています。
- 修士論文指導:財務会計分野、税法分野の修士論文指導に力を入れています。
千葉商科大学会計大学院
千葉商科大学の会計大学院は、税理士試験の科目免除申請に対応しており、特に社会人が学びやすい環境が整備されています。
- オンライン授業の充実:平日夜間と土日昼間に開講しており、2020年度からはオンライン授業のみでの学位取得が可能になりました。遠隔地の学生でも税法論文の執筆を目指せます。
- 専門実践教育訓練給付金:会計プロフェッションコースと税務プロフェッションコースは、専門実践教育訓練給付金の指定講座となっており、最大112万円の支給が可能です。
- 段階的な教育方法:初学者でも無理なく専門知識を学べるよう、基礎・発展・応用実践の3段階教育方法を実施しています。
武蔵野大学
武蔵野大学は、税理士受験に特に力を入れている大学院として注目されています。
- 資格試験予備校との提携:資格試験予備校と提携し、一人ひとりに担当がつき、合格までサポートする体制が整えられています。
- 充実した奨学金制度:大学学費と予備校学費を合わせて4年間で最高500万円まで支給される奨学金制度があるなど、経済的支援が手厚いです。
明治大学専門職大学院会計専門職研究科
明治大学は公認会計士の合格実績も高いですが、税理士の科目免除にも対応しており、特に税務専修コースの院試は比較的合格しやすいとの意見もあります。
- 税務専修コース:会計専修と税務専修の2コース制を採用し、税理士を目指す学生のニーズに応じた科目履修が可能です。
- メディア授業の拡充:昼夜開講制に加えてメディア授業を積極的に拡充しており、有職社会人でも修了しやすいカリキュラムです。
- 経理研究所:学内に公認会計士・税理士試験対策のための経理研究所があり、費用を抑えつつサポートを受けられる利点があります。
中央大学
中央大学も、明治大学と同様に公認会計士の合格者数が多く、税理士受験対策にも力を入れています。
- 経理研究所:学内に経理研究所があり、税理士受験対策を行っています。ただし、予備校とのダブルスクールが必要になることが多いという見解もあります。
甲南大学大学院 社会科学研究科
甲南大学大学院は、税理士としての実務に直結する教育が受けられる点が特徴です。
- 幅広い分野の学習: 租税法、経営学、会計学など幅広い分野を学べます。
- 柔軟なカリキュラム: 社会人を対象とした柔軟なカリキュラム設計が魅力で、自身のスケジュールに合わせて学びを進めることが可能です。
- 租税法の充実: 租税法の充実したカリキュラムと専門的な教授の経験が際立っており、修士論文のテーマ選定から提出までのサポート体制も整っています。
- 穏やかな受験倍率: 全国的に見て受験倍率が比較的穏やかでありながら、研究環境が整備され、中小企業の租税問題に関する現実的なケーススタディも豊富です。
立正大学大学院 経営学研究科
立正大学大学院は、心豊かな産業人の育成を目標とし、税理士のキャリアにおいて競争力を高める教育を提供しています。
- 実務系の知識:会計学や経営学に加え、マーケティングや情報システム学といった実務系の知識も学べます。
- 実践的ビジネススキル:修士論文の執筆を通じて、理論だけでなく、現場での問題解決力も磨かれる仕組みがあります。
- 社会人学生への支援:働きながら税理士資格取得を目指す方にとって最適な学習環境を提供しており、一部科目はオンライン講座で履修可能です。
熊本学園大学大学院会計専門職研究科
熊本学園大学は、岡山県以西で唯一の会計専門職大学院であり、少人数教育に力を入れています。
- 網羅的な税法科目:総論としての租税法原理だけでなく、法人税、所得税、消費税、相続税等についての個別科目をそれぞれ開講し、租税法分野での論文作成指導にも力を入れています。
- 実務家教員による実践科目:財務会計、管理会計、監査、および租税法についての実務家教員による演習科目を設け、実践的な能力の涵養に努めています。
- 社会人への配慮:平日夜間と土日開講の「ウィークエンド・コース」や、3年間で修了できる長期履修制度を設けています。
- 少人数教育と論文指導:1学年定員30名の少人数クラスで質の高い教育を提供し、個別的な論文指導に力を入れています。
兵庫県立大学大学院社会科学研究科
兵庫県立大学は関西地方の会計専門職大学院として推奨されており、理論と実務の架橋教育を重視しています。
- 税務に関するケーススタディ:租税法ケーススタディでは、税理士事務所や国税局・税務署を訪問し、実務家と質疑応答を行う実践的な学びがあります。
- 少人数教育:神戸商科大学の伝統を受け継ぎ、演習系の科目では教員1人につき学生5人程度という少人数教育を徹底しています。
青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科
青山学院大学は、専門性に応じた2つの教育プログラムと修学期間の異なる3つのコースを提供しています。
- 専門性に応じたプログラム: 財務会計・監査中心の「会計監査プログラム」と、租税法・管理会計・経営学中心の「税務マネジメントプログラム」があります。
- 柔軟な修学期間と時間割: 2年制に加え、実務経験3年以上の社会人向けの1年半制、資格保有者向けの1年制コースがあり、平日昼夜間、土曜日の通常講義と集中講義(日曜、春・夏休み)を組み合わせることで、仕事や資格試験との両立が可能です。
- 充実した学習環境: 1年中使える自習室と、公認会計士試験対策・税理士試験対策のための特別演習講座が用意されており、在学中だけでなく修了後も資格取得を支援します。
関西大学会計専門職大学院
関西大学会計専門職大学院は、世界で通用する、理論と実務に習熟した会計専門職業人を養成することを目指しており、8つの魅力があるのが特徴です。
- 豊富な授業科目: 会計を中心に、基本から発展、応用・実践へとレベルに応じた学修が可能で、演習・事例研究も多様に展開されています。
- 最適な学習環境: 専用の自習室・パソコン教室は24時間365日利用が可能で、自分の生活スタイルに合わせた学修が可能です。
- 充実の奨学制度: 高度な資格取得者や成績優秀者に対する給付奨学金など、豊富な奨学制度が用意されており、公認会計士試験(短答式)合格者には授業料1年全額相当分、簿記検定1級合格者には授業料1年半額相当分が給付されます。
- 各種試験への対応: 「資格の学校TAC」と提携した課外講座を開講し、公認会計士試験合格を支援するほか、主要講義の動画配信も行われています。
- 長期履修学生制度: 2年の標準修了期間を3年または4年に延長できる制度があり、社会人でも働きながら学修しやすい環境です。
関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科
関西学院大学の会計専門職専攻は、会計プロフェッションコースとリカレントコースの2本立てで、国際的な水準で経済社会に貢献できる職業会計人の養成を目指しています。
- 柔軟性が高いカリキュラム: 昼・夜と土曜日に開講しており、平日夜は大阪梅田キャンパスでも授業が行われます。平日夜間と土曜日の受講、あるいは年間32回の土曜日通学と夏冬の集中講義(各1週間程度)のみで修了可能です。
- 幅広い知識: 会計の基礎から実践に加え、ビジネススクールの科目も10単位まで履修可能で、会計にとどまらないビジネスに関する最新の理論や実践的な知識が得られます。
- 強力なOB・OG組織: 関西学院大学同窓の公認会計士の組織「弦月CPA会」が就職・就職後もバックアップし、学生・修了生を支援します。
東北大学大学院経済学研究科会計専門職専攻
東北大学は、公認会計士を目指す「公認会計士コース」、税理士試験の一部科目免除や博士後期課程進学希望者を視野に入れた「会計リサーチコース」、社会人のリカレント教育を目指す「ビジネスアカウンティングコース」の3コース制を採用しています。
- 少人数教育の徹底: 1学年定員40名に対して17名の教員が配置されており、きめ細やかな教育が実施可能です。学生ごとに担任教員が置かれ、修了後のキャリアから履修科目の選択、学習の進め方に至るまで幅広い指導や相談に対応します。
- 国際的な人材の養成: 外国人教員を配置し、英語教育の充実を図ることで、国際化する会計士業務やビジネスに対応した教育を提供します。
- 非会計分野の教育充実: 会計学のみならず、経済学、経営学、統計学、ITなどの情報処理技術といった会計隣接領域の科目を体系的に開講し、高度な分析能力を持つ職業会計人の育成を目指しています。
北海道大学大学院経済学院会計情報専攻
北海道大学の会計情報専攻は、複雑化した現代社会に対応する充実のカリキュラムと徹底した少人数教育が特徴です。
- 複雑化した現代社会に対応するカリキュラム: 財務会計、管理会計、監査、税務会計の会計4分野をバランスよく履修できるようカリキュラムが編成されており、倫理観・社会的責任感を養う「会計職業倫理」が必修です。
- 徹底した少人数教育: 1学年定員20名と少人数で、教員から学生への対話型講義に加え、学生同士の活発な議論を重視します。修士論文を修了要件としていない点が大きな特徴ですが、希望する学生は執筆可能です。
- きめ細やかな修学サポート: 学生5名程度に1人の担任が配置され、全専任教員がオフィスアワーを設定して学生の学習環境の充実を図っています。院生研究室には、机とロッカーが各人に割り当てられており、理想的な学習環境が提供されています。
早稲田大学大学院会計研究科
早稲田大学の会計研究科は、「アカウンティング+1、アクチュアリー+1」というコンセプトを掲げ、専門家集団の中でも飛びぬけた実力を持つ人材の養成を目指しています。
- 多様な専門領域の学習: 会計専門コースやアクチュアリー専門コースに加え、ICT・コンサルティング、Professional Communication、税務、データサイエンスといった今日の専門家には不可欠な領域を準備しており、学生のニーズに応じて学習できるようになっています。
- ワークショップ科目と論文執筆: ゼミ形式のワークショップ科目や論文執筆を行うテーマ研究科目が用意されており、議論を通じて自身の考えを文章としてまとめる能力を養います。修了生からは、ワークショップの授業を通して、知識を実践的に活かすための思考力が身についたとの声があります。
その他の大学院
- 東亜大学法学専攻大学院:税法2科目免除で全国的に人気があり、入試の倍率は高いものの、教授陣が充実しているとされています。
- 滋賀大学:税理士・公認会計士の対策講座受講費用を援助する「会計スペシャリスト育成支援制度」を提供しています。税理士試験科目合格者への受験料補助金給付もあります。
- 名古屋商科大学大学院:3年間で最大3科目の免除が可能であり、MSc in Taxationの学位が授与されます。
- 九州国際大学:税法免除を行っている大学院の一つであり、比較的入学しやすいとされています。
これらの大学院は、それぞれ異なる強みや特色を持って税理士科目免除を目指す学生を支援しています。自身の学習スタイル、キャリア目標、経済状況などを総合的に考慮し、各大学院の公式ホームページで最新の情報を確認した上で、最適な進学先を選択することが重要です。
税理士試験の科目免除制度の概要
税理士資格の取得を目指す上で、会計大学院(専門職大学院)への進学は、税理士試験の科目免除制度を利用できるという大きなメリットをもたらします。税理士試験は全11科目の中から5科目に合格する必要がある難関ですが、この制度を活用することで、試験準備の負担を軽減しつつ効率的な資格取得を目指すことが可能になります。
免除制度の仕組みと対象科目
税理士試験の科目免除制度は、大学院で税法や会計学に関する分野を深く研究し、修士論文を提出して所定の単位を取得することによって適用されます。具体的には、税法に関する修士論文が国税審議会の審査で認定されれば税法科目が2科目、会計学に関する修士論文であれば会計学科目が1科目、それぞれ免除される仕組みです。この制度は、特に社会人や既に実務に携わる方々にとって、専門的な知識を体系的に学ぶ機会となりながら、試験の負担を軽減できる点で有益とされています。
科目免除を受けるためには、単に大学院を修了するだけでなく、国税庁が定めた基準を満たした大学院で学ぶ必要があり、修士論文が厳正な審査を通過することが要件となります。このため、自身の研究テーマに合った教授が在籍し、多角的な研究支援体制が整っている大学院を選ぶことが重要です。
「ダブル院卒」による複数科目免除
さらに、特定の条件下では、より多くの科目を免除できる可能性もあります。例えば、商学系と法学系の異なる大学院でそれぞれ修士号を取得する、いわゆる「ダブル院卒」のルートでは、会計科目1科目と税法科目2科目の合計3科目の免除が目指せるとされています。しかし、このルートを選択する場合、平成14年度以降の進学者には、免除を受ける前に最低1科目ずつの会計科目と税法科目を自力で合格していることが求められます。また、学費が高額になる傾向があり、就職活動において5科目すべてを試験で合格した人と比較して不利になる可能性も指摘されているため、慎重な検討が必要です。
免除制度の現状と留意点
近年、税理士試験の科目免除における修士論文の審査は厳格化が進んでいるとされています。かつて「確実に免除が取れる」とされていた大学院があったとしても、現在は安易な免除は期待できないという見解も存在します。
また、科目免除によって税理士資格を取得した場合、就職の際に5科目すべてを試験で合格した人と比べて評価が低いとされるケースがある点も留意すべきでしょう。特に、法人税法などの主要科目を免除で取得した場合、一般的な税理士事務所への就職が難しくなる可能性が指摘されており、会計事務所は資格そのものよりも実務経験を重視する傾向があります。
このように、税理士試験の科目免除制度は資格取得への有効な選択肢の一つである一方で、その利用には、大学院選び、論文の質、そして将来のキャリアパスにおける評価など、多角的な視点からの慎重な検討が求められます。
大学院進学のメリット

税理士資格や公認会計士資格の取得を目指す上で、会計大学院(専門職大学院)への進学は、試験の負担を軽減しつつ、専門知識を体系的に深めるという大きなメリットを提供します。会計大学院は、単なる資格試験対策の場ではなく、「会計のプロフェッショナル」の養成を目的とした教育機関です。
試験負担の軽減(科目免除制度)
大学院進学の最大の魅力の一つは、税理士試験および公認会計士試験における科目免除制度を利用できる点です。この制度は、資格取得への道のりを効率化し、学習負担を大幅に軽減する可能性があります。
税理士試験の科目免除
税理士試験は全11科目の中から5科目に合格する必要がある難関ですが、大学院で税法または会計学に関する修士論文を提出し、国税審議会の審査で認定され、所定の単位を取得することで、特定の科目が免除されます。具体的には、税法に関する修士論文が認定されれば税法科目が2科目、会計学に関する修士論文であれば会計学科目が1科目免除となります。
さらに、商学系と法学系の異なる大学院でそれぞれ修士号を取得する、いわゆる「ダブル院卒」のルートでは、会計科目1科目と税法科目2科目の合計3科目の免除を目指せるとされています。ただし、平成14年度以降の進学者には、免除を受ける前に最低1科目ずつ会計科目と税法科目を自力で合格していることが求められます。このルートは学費が高額になる傾向がある点に留意が必要です。
免除制度に力を入れている大学院の例としては、武蔵野大学、中央大学、明治大学、千葉商科大学、名古屋商科大学大学院、東亜大学、滋賀大学、九州国際大学、九州情報大学などが挙げられます。
公認会計士試験の科目免除
会計大学院を修了することで、公認会計士試験の短答式試験(1次試験)のうち、財務会計論、管理会計論、監査論の3科目が免除されます。短答式試験は合格率が約10%と低く、受験者の94%以上が不合格となる難易度の高い試験であるため、この3科目の免除は受験生にとって極めて大きなメリットとされています。免除されることで、残りの「企業法」1科目の受験で短答式試験を通過でき、合格率約30%の論文式試験(2次試験)に進むことが現実的に可能になります。
学問的深化と専門性の獲得
会計大学院は、単なる資格試験の対策機関に留まらず、会計に関する高度な専門知識と実務に直結する能力を体系的に学ぶ場を提供します。
- 体系的な知識習得: 経営学や会計学などを体系的に学び、会計プロフェッショナルとしての基盤を築きます。講義は理論的な深さと実践的な側面を兼ね備え、知識が実務にどう繋がるかを理解できます。
- 実務に即したカリキュラム: 現役で活躍する会計士や実務家が教員を務めることが多く、ケーススタディなどを通じて最先端の専門知識や問題解決能力を磨くことができます。これにより、単なる知識の暗記に終わらず、実務で活用できる深い理解と応用力が身につきます。
- 幅広い知識と多角的な視点: 会計大学院では、公認会計士試験には出題されない範囲や周辺分野の学問(例:マーケティング、情報システム学、国際会計基準(IFRS)、データサイエンスなど)も学ぶことができ、将来のキャリアにおける競争力を高めます。これにより、税理士として事業承継、M&A、国際税務など、より高度で幅広いニーズに対応できる素養を養うことが期待されます。
- 思考力と表現力の向上: 論文執筆や演習、ディスカッションを通じて、論理的思考力、問題解決力、コミュニケーション能力、文章作成能力が向上します。これは、実務において複雑な問題を分析し、根拠に基づいた判断や説得力のある提案を行う上で非常に役立ちます。
その他のメリット
上記以外にも、会計大学院への進学は、キャリア形成や学習環境の面で様々な利点をもたらします。
- 「専門職修士」の学位と経歴: 会計大学院を修了すると、「専門職修士」の学位が授与され、大学卒業後に資格取得を目指す期間が経歴上の空白となることを避け、学歴として記載できます。
- 人脈形成の機会: 会計大学院には、会計業界で活躍する教員や、多様な経歴を持つ社会人学生(弁護士、官公庁職員、大手企業在職者など)が集まります。これにより、将来的に役立つ貴重な人脈を築く機会が得られます。
- 学習環境とモチベーション維持: 試験勉強に専念できる環境が整い、同じ志を持つ仲間との出会いは、モチベーションの維持に繋がります。専用の自習室や充実した図書館、オンライン講義の提供など、学習を支援する環境が整備されている大学院も多いです。
- 柔軟な学習スケジュール: 多くの会計大学院では、社会人が働きながら学びやすいよう、平日夜間や土日、オンラインでの授業など、柔軟なカリキュラムが用意されています。
- 経済的支援: 成績優秀者向けの学費免除や半額制度、日本学生支援機構の奨学金、各大学独自の奨学金、あるいは予備校学費を含めた奨学金制度を提供する大学院も存在します。
- 就職の「保険」: 公認会計士試験の合格は難関であるため、万が一在学中に合格できなかった場合でも、大学院修了という学歴が新卒としての就職活動における「保険」となり得るという側面もあります。
これらのメリットは、単に資格を取得するだけでなく、高度な専門性を持ち、将来のキャリアを豊かにするための投資としての会計大学院の価値を示しています。
大学院進学のデメリット
会計大学院への進学は、会計士や税理士といった専門職を目指す上で多くのメリットを提供しますが、同時に無視できないデメリットも存在します。特に、経済的な負担と時間の投資は、進学を検討する上で慎重に考慮すべき重要な要素です。
学費の高さと経済的負担
会計大学院の学費は、専門学校や受験予備校と比較して高額になる傾向があります。
学費の目安
- 国立大学の会計大学院の場合、2年間で約130万円から150万円ほどが目安とされています。これには入学金約28万円、年間授業料約54万円程度が含まれます。
- 私立大学の会計大学院では、2年間で250万円から350万円以上と、さらに高額になる可能性があります。入学金は国公立と同程度の20万円から30万円台が相場ですが、年間授業料が高額な場合は150万円に達することもあります。
これらの他に、年間数万円から10万円程度の施設費などがかかる場合もあります。
経済的リスク
正社員を辞めて大学院に進学する場合、在学中の収入が途絶えたり激減したりするため、資格取得に失敗した場合の経済的リスクが非常に大きくなります。特に28歳前後で結婚やマイホーム購入を意識する年齢の場合、この費用負担は決して軽くありません。
奨学金制度(日本学生支援機構や大学独自の奨学金、予備校学費を含めた奨学金など)や、学費を分割して支払うことが可能な長期履修制度の活用も可能ですが、それでもかなりの負担となる額です。
修了までの時間とキャリアへの影響
会計大学院の標準的な修了年限は2年間です。この期間は、キャリア形成や社会に出るタイミングに影響を与える可能性があります。
時間的な制約
会計大学院での学習は、公認会計士試験の受験勉強以外の学業にも時間を費やすことになります。特に修士論文の作成には相応の時間と労力が求められる場合もあります。
キャリアの空白期間
大学卒業後に就職せずに会計大学院に進学する場合、合格するまでの期間が経歴上の空白となる可能性があります。修了後すぐに資格を取得し、キャリアパスが明確であれば問題ないものの、社会に出るのが遅れることで、転職や就職の選択肢が狭まる可能性も指摘されています。近年、企業側が資格取得者よりも「実務経験」を重視する傾向が強まっているため、大学院での2年間がキャリアの空白期間と捉えられ、かえって不利になるケースも少なくありません。
モチベーション維持の難しさ
大学院の勉強に追われて、肝心の会計士試験の勉強時間が減り、結果的に合格できないまま諦めてしまうケースも報告されています。
試験合格への直接的な効果の薄さ
会計大学院は「会計のプロフェッショナル」の養成を目的とした教育機関であり、予備校のように「資格試験に合格させること」を目的としているわけではありません。
ダブルスクールの必要性
多くの情報源が、会計大学院の授業だけでは公認会計士試験の受験対策として不十分であり、専門学校とのダブルスクールが実質的に必要となるケースがほとんどだと指摘しています。これにより、学費が高額になるだけでなく、学習負担も増大します。
学習内容と試験の乖離
大学院の授業や課題が、専門学校での受験勉強の負担になることもあります。大学院には試験対策に関する蓄積されたノウハウが基本的にないため、予備校の方が優っているという指摘もあります。
合格率の現実
大学院修了者だけの公認会計士試験合格率に絞っても、30%を超える大学院はほとんどなく、一般的なイメージほど合格のハードルは低くありません。「会計大学院に進学しても公認会計士試験に合格しやすくなるわけではない」と明言する意見もあります。
科目免除の限定的価値と就職への影響
会計大学院の大きなメリットとされる科目免除制度にも、注意すべき点があります。
公認会計士試験
会計大学院を修了すると、公認会計士試験の短答式試験(1次試験)のうち「財務会計論」「管理会計論」「監査論」の3科目が免除されますが、論文式試験(2次試験)には一切免除がありません。論文式試験が最大の難関であり、この免除を目当てにした進学は推奨されないという意見もあります。
税理士試験
大学院で税法または会計学に関する修士論文を提出し、国税審議会の審査で認定されれば科目免除は可能ですが、論文審査が厳しくなっており、安易な免除は期待できないという見解もあります。
就職への評価
税理士業界では、科目免除で資格を取得した場合、5科目すべてを試験で合格した人と比べて評価が低いとされることがあります。特に「法人税法」を免除で取得した場合、通常の税理士事務所での就職が困難になる可能性が高いと指摘されています。会計事務所は資格よりも実務経験を重視する傾向があります。
年齢と経験
40歳前後で経理未経験の場合、大学院で税理士資格を取得しても、実務経験がないため会計事務所への就職は難しいとされています。
学習レベルと適性の課題
会計大学院の学習レベルは高く、入学前の準備や自身の適性が重要です。
高い専門性
会計大学院の講義レベルは高く、日商簿記2級程度の知識ではついていくのが難しいとされています。在学生の多くは日商簿記1級を「楽勝」と感じる程度の知識を持っていることが多いです。
入学前の準備不足
日商簿記3級程度の知識から公認会計士を目指して大学院への進学を考えるのは時期尚早であり、まず日商簿記2級、さらには1級へと段階的に勉強を進めることが推奨されています。
曖昧な目的意識
「会計が好き」といった漠然とした理由での進学は勧められていません。「学ぶに足る意思」「的確な問題意識」「多量な予習に耐えられるタフさ」が重要だとされています。目的意識を持たずに通学しても、思うように勉強内容を活かせず、時間を無駄にしてしまう可能性もあります。
これらのデメリットを総合的に考慮し、自身のキャリア目標、経済状況、学習スタイルと照らし合わせ、冷静かつ慎重に進学の判断をすることが、後悔しない選択のために不可欠です。
税理士科目免除が可能な大学院の評価基準
税理士試験の科目免除が可能な大学院は、その学術的な要件と実務家養成の目的を両立させるために、特定の基準を満たす必要があります。これらの基準は、大学院が税理士を目指す学生に対して、適切な教育環境と免除申請の道を提供できるかを評価する上で重要な指標となります。
免除制度の基盤となる要件
税理士試験の科目免除を受けるためには、大学院で税法や会計分野に関する修士論文を提出し、所定の単位を取得することが必須です。具体的には、修士論文が国税審議会の審査で認定されることが求められます。税法関連の論文であれば税法2科目が、会計学関連の論文であれば会計学1科目が免除対象となります。ただし、平成14年度以降に進学した場合は、免除を受ける前に会計科目と税法科目を最低1科目ずつは自力で合格している必要があるという条件も存在します。
教授陣の専門性と指導力
科目免除が可能な大学院を選ぶ上で、教授陣の専門性と指導力は極めて重要な要素です。特に、租税法や会計学の専門知識を持つ教授がどれだけ在籍しているかが、修士論文の指導や研究環境を左右します。税理士試験の科目免除を目指す場合、修士論文の指導ができる教授がいる大学院を選ぶ必要があり、同じ大学院内でも研究科によって指導の可否が異なるため、事前の確認が不可欠とされています。また、多角的な研究支援体制が整っている大学院は、よりスムーズに科目免除の手続きを進められる可能性を高めます。
カリキュラムの内容と研究環境
免除制度が整備されているか、そしてその条件やカリキュラムの内容が明確であり、税理士試験の要件を満たしているかどうかも評価基準となります。大学院での学習は、税法や会計学といった実務に直結する知識を体系的に学べる場でもあります。質の高い研究を支援するためには、豊富な研究費、充実した研究設備や施設も利点となり得るとされています。
論文審査の厳格化と現実
かつては「確実に免除を取れる」と謳う大学院もあったものの、近年は論文審査が厳しくなっており、安易な免除は期待できないという見解もあります。これは、免除制度の利用を検討する学生にとって、修士論文作成に相応の時間と労力が求められることを意味します。そのため、事前に大学院のカリキュラムや教授の専門分野を調査し、自身の目標に合致する選択をすることが重要です。
卒業生の実績と就職状況
卒業生の合格実績や就職状況も、大学院ランキングの信頼性を高めるポイントとなります。特に税理士業界では、科目免除で資格を取得した場合、5科目すべてを試験で合格した人と比べて評価が低いとされることがあるため、大学院がどのようなキャリアパスを支援しているかを確認することも重要です。
オンラインや夜間の対応状況
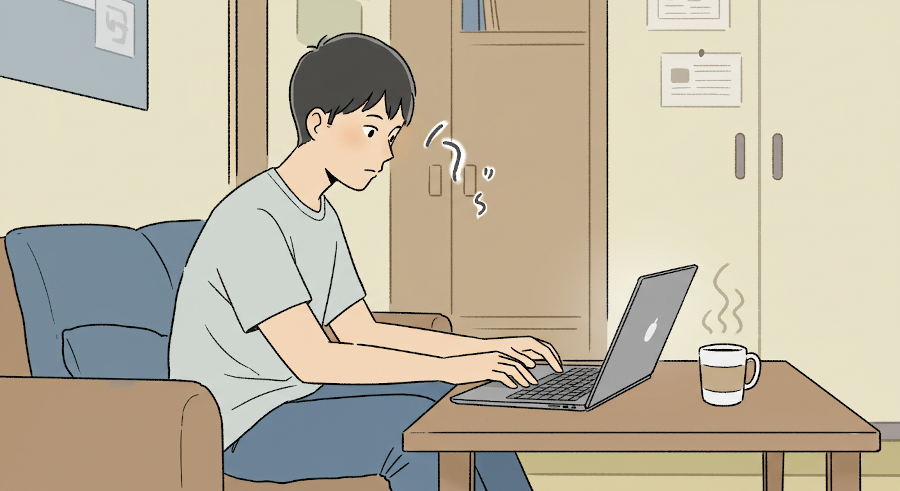
税理士資格取得を目指す社会人学生にとって、大学院進学における学習環境の柔軟性は非常に重要な要素です。多くの大学院が、多忙な社会人が学びを継続できるよう、オンライン講座や夜間開講、長期履修制度など多様な学習支援を提供しています。
各大学院の柔軟な学習環境
いくつかの大学院では、以下のような柔軟な学習環境を整備しています。
- 甲南大学大学院 社会科学研究科: 社会人を対象とした柔軟なカリキュラム設計が魅力であり、自身のスケジュールに合わせて学びを進めることが可能です。
- 立正大学大学院 経営学研究科: 一部科目がオンライン講座で履修可能であり、社会人学生への手厚い支援を通じて、働きながら税理士資格取得を目指す方にとって最適な学習環境を提供しています。
- 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科: 平日昼夜間および土曜日の通常講義に加え、授業期間中の日曜や春休み・夏休みの土日にも集中講義を開設しており、仕事や資格試験との両立を可能にしています。必修科目と選択必修科目は昼間だけでなく平日夜間や土曜日にも配置されており、順調に単位を修得すれば平日夜間と土曜日のみの通学で標準年限で修了することも可能です。
- 大原大学院大学会計専門職大学院: 都心にキャンパスを構え、昼夜開講制を採用しているため、働きながら学ぶ社会人学生が多く在籍し、資格取得を目指せる利便性があります。
- 関西大学会計専門職大学院: 長期履修学生制度を設けており、標準の2年間を3年または4年に延長することで、年間の履修科目を減らし、働きながら学修を進めるメリットがあります。この制度を利用しても学費は2年修了とほぼ変わりません。
- 関西学院大学専門職大学院 経営戦略研究科: 昼間、夜間、土曜日に授業を開講しており、平日夜間は通学に便利な大阪梅田キャンパスでも授業を行っています。平日夜間と土曜日の受講、あるいは年間32回の土曜日通学と夏冬の集中講義(各1週間程度)の受講でも修了可能な柔軟性の高いカリキュラムが特徴で、遠隔地の社会人でも通学しやすい環境です。
- 熊本学園大学大学院会計専門職研究科: 平日の講義を履修する「平日コース」に加えて、金曜日の夜間と土曜日・日曜日に開講される講義を履修する「ウィークエンド・コース」を設けています。ほぼすべての主要科目が両コースで同一内容で開講されており、「ウィークエンド・コース」の講義のみで修了することも可能です。また、3年間で必要単位を取得して修了する長期履修制度も提供しており、多忙な社会人に合わせたカリキュラムが組まれています。
- 千葉商科大学会計大学院: 働きながら学べる環境が整備されており、平日夜間と土日昼間に開講されています。基本的に土日の受講のみで修了要件を満たすことが可能です。さらに、開講授業の30%が遠隔(オンライン)形式で提供されており、2020年度からは税務プロフェッションコース(論文あり)に限りオンライン授業のみでの学位取得も可能となっています。
- 明治大学専門職大学院会計専門職研究科: 昼夜開講制に加え、メディア授業を積極的に拡充することで、有職社会人でも修了しやすいカリキュラムを編成しています。
- LEC東京リーガルマインド大学院大学(LEC会計大学院): 全てのコースがオンラインのみで完結可能である点が最大の特徴で、日本全国から海外在住の社会人学生が学んでいます。学生の平均年齢は38.7歳で、約9割が現職を持ちながら学んでいます。全科目がオンラインライブ授業で、ほとんどの必修科目と修士論文指導は土日に集中して配置されているため、土日中心の履修が可能です。また、講義資料や動画の共有、オフィスアワー、懇親会といったコミュニケーションツールもクラウド上で提供され、忙しい社会人でも効率的に学習できる仕組みが整っています。
これらの大学院は、社会人がキャリアを中断することなく税理士資格の取得や専門知識の深化を目指せるよう、学習時間や場所の制約に対応した多様な選択肢を提供しています。長期履修制度を利用することで、学費を分割して支払うことも可能です。
会計大学院はどこがいい?選択のポイントと注意点
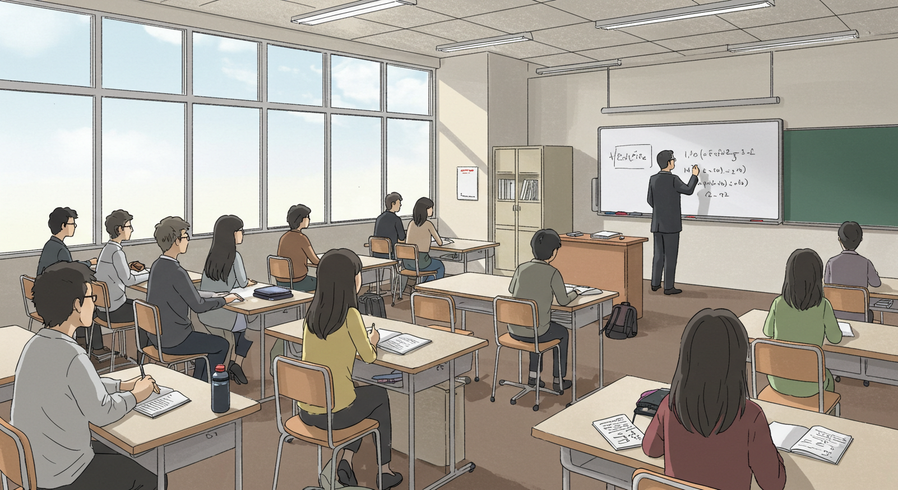
- 大学院選びの重要ポイントとチェックリスト
- 研究テーマ選定と修士論文作成の要点
- 大学院入試の準備と選考で求められる要素
- 大学院修了後の税理士としてのキャリア展望
- 実務で活かせる知識・スキルと人脈形成
- 会計大学院進学における主な注意点
大学院選びの重要ポイントとチェックリスト
税理士資格取得を目指す社会人学生にとって、大学院選びは自身のキャリア形成と学習の継続性を左右する極めて重要なプロセスです。多忙な社会人が学びを継続できるよう、多くの大学院が多様な学習支援を提供しており、自身の目標とライフスタイルに合致した選択をすることが成功への鍵となります。
大前提となる確認事項
大学院を選ぶにあたり、まず確認すべきは以下の基本的な点です。
税理士試験の科目免除制度への対応
税理士資格取得を目指す場合、進学を検討している大学院が税理士試験の科目免除制度に対応しているかを確認することが不可欠です。この制度では、大学院で税法や会計分野に関する修士論文を提出し、所定の単位を取得することで、税法2科目または会計学1科目の免除が得られる可能性があります。ただし、免除制度の詳細は研究分野やカリキュラムによって異なるため、具体的な条件を大学院に直接確認することが重要です。修士論文の作成には相応の時間と労力が求められ、論文審査が厳しくなっているとの見解もあります。
自身のキャリア目標との合致
大学院の教育方針やカリキュラムが、自身の目指すキャリアや学習目標(資格取得、高度な専門性の獲得、就職、学歴など)と合致しているかを慎重に確認することが重要です。
具体的なチェックポイント
上記の大前提を踏まえ、さらに具体的な選択基準を検討しましょう。
学習環境の柔軟性
社会人学生にとって、学習を継続できる環境が整っているかは非常に重要です。
- オンライン・夜間・週末開講の有無: 多くの大学院が、平日昼夜間、土曜日、または日曜日の集中講義といった柔軟な時間割を提供しています。LEC東京リーガルマインド大学院大学のように、全コースがオンラインのみで完結可能な大学院もあります。
- 長期履修制度: 標準の修了期間(通常2年)を3年や4年に延長し、年間の履修科目を減らすことで、働きながら学修を進められる制度です。学費が2年修了とほぼ変わらない場合もあります。
- 通学のしやすさ: 自宅や職場からの通学経路や、主要な予備校へのアクセスが良いかどうかも考慮すべき点です。
- 学習設備: 24時間利用可能な自習室や、充実したネットワーク環境、図書館などの設備が提供されているかどうかも、効率的な学習に影響します。
教育内容と教授陣の質
専門知識を深く学ぶためには、質の高い教育と指導が不可欠です。
- 教授陣の専門性: 税法や会計学を専門とする教授が複数在籍しているか、自身の興味関心と指導教授の専門分野が一致しているかを確認しましょう。
- 修士論文指導のサポート: 税理士の科目免除を目指す場合、修士論文のテーマ選定から提出までのサポート体制が整っているかどうかが重要です。LEC会計大学院では、主査教授に加えて構成指導や文章指導の担当教員がつき、チーム制で指導を行う体制を整えています。
- 実践的なカリキュラム: 理論だけでなく、実務に直結する知識や問題解決能力を養えるカリキュラムが提供されているかを確認しましょう。例えば、東北大学大学院では、経済学、経営学、統計学、ITなどの会計隣接領域の知識も体系的に学べる機会があります。
- 少人数教育: 甲南大学大学院、熊本学園大学大学院、東北大学、兵庫県立大学、北海道大学など、少人数教育を徹底し、きめ細やかな指導を行う大学院も存在します。
経済的側面と支援制度
大学院進学は大きな投資となるため、費用と経済的支援について十分に把握しておく必要があります。
- 学費: 国立大学院は年間約80万円以上、私立大学院は年間150万円以上が一般的で、2年間で合計130万円から350万円以上かかる場合があります。
- 奨学金・学費免除制度: 日本学生支援機構の奨学金、各大学独自の奨学金制度、民間団体の奨学金、成績優秀者に対する学費免除や半額制度などを活用することで、経済的負担を軽減できる可能性があります。例えば、武蔵野大学では大学学費と予備校学費を合わせて最高500万円まで支給される奨学金制度があります。
資格取得・キャリアサポート
大学院での学びが将来のキャリアにどう繋がるかを確認することも重要です。
- 資格試験対策: 学内に公認会計士試験対策のための経理研究所を持つ大学院(例: 明治大学、中央大学)や、資格予備校と提携した課外講座を提供する大学院(例: 関西大学、大原大学院大学、武蔵野大学)もあります。
- 卒業生の合格実績と進路: 大学院ランキングや卒業生の合格実績、就職状況は、大学院選びの有益な情報源となりますが、主観的な要素も含まれるため、自身の目標と照らし合わせて検討することが大切です。
- 人脈形成の機会: 会計大学院には多様な経歴を持つ社会人が集まるため、教員や学生との交流を通じて将来のキャリアに役立つ人脈を築く機会が得られます。関西学院大学や熊本学園大学のように、同窓会組織との連携が密な大学院もあります。
入学前の準備と適性
入学試験の準備だけでなく、自身の適性や学習計画を具体的に立てることが重要です。
- 入学試験: 一般的に学力試験(経済学、経営学、会計学などの基礎知識)、研究計画書、面接が選考基準となります。特に研究計画書は合否を大きく左右する重要な書類であり、自身の研究テーマや目標を論理的に説明する必要があります。
- 必要な学力レベル: 会計大学院の授業レベルは高く、多くの在学生は公認会計士受験生であり、日商簿記1級レベルの知識を「楽勝」と感じる程度と評されています。入学前に簿記2級、できれば1級へと段階的に学習を進めることが推奨されています。
- スケジュール管理: 在職中の社会人学生は、学習時間を確保し、仕事、授業、プライベートのバランスを保つための徹底したスケジュール管理が成功の鍵となります。
これらの要素を総合的に比較検討し、ご自身の現在の状況と将来の目標に最も適した大学院を選択することが、税理士資格取得とキャリア形成の両面において成功への近道となるでしょう。
研究テーマ選定と修士論文作成の要点
税理士資格取得を目指す上で、大学院における研究テーマの選定と修士論文の作成は、科目免除制度を活用する上で極めて重要な要素となります。税理士試験の科目免除制度は、大学院で税法や会計分野に関する修士論文を提出し、所定の単位を取得することで適用されるため、その内容は免除の可否を左右するからです。修士論文の作成には相応の時間と労力が求められるだけでなく、免除制度の要件を満たす大学院でなければ科目免除が受けられない点にも注意が必要です。また、国税庁が定めた基準を満たし、修士論文で税法や会計学に関するテーマを深く研究し、論文審査を通過することが要件とされています。
研究テーマ選定の要点
修士論文の研究テーマを選定するにあたっては、まず自身の興味関心を明確にすることが第一歩となります。例えば、租税法や国際会計など、特定の分野に焦点を絞ることで論文の方向性が定まりやすくなります。
さらに重要なのは、指導教授の専門分野が自身の興味と一致しているかを確認することです。教授の専門性がテーマと合致していれば、よりきめ細やかな指導やサポートが期待できます。研究テーマは、単なる学術的興味だけでなく、実践的かつ学術的な価値を兼ね備えていることが望ましいとされています。これは、税理士としての実務に直結する知識や問題解決能力を養う上で不可欠な視点です。過去の修士論文の傾向を大学院から取り寄せることも、自身のテーマを構築する上で有益な参考情報となるでしょう。
修士論文作成の要点とサポート体制
修士論文の作成は、体系的な知識の習得だけでなく、論理的思考力や文章作成能力を磨く機会でもあります。多くの大学院がこのプロセスを支援するための多様なサポート体制を整えています。
指導教授によるサポート
論文執筆が初めての学生でも、指導教授の的確なサポートにより論文を完成させることが可能です。例えば、大原大学院大学では、指導教授による細やかなサポートが行われています。熊本学園大学大学院でも、個別的な論文指導に力を入れており、ほとんどの学生が学位論文を作成して修了しているとされています。
少人数教育とディスカッション
少人数クラスでの密度の高い教育は、担当教員との密接なコミュニケーションを可能にし、質の高い指導につながります。例えば、神戸商科大学の伝統を受け継ぐ兵庫県立大学大学院では、演習系の科目で教員1人につき学生5人程度としています。北海道大学大学院では、教員と学生の距離が近く、対話型講義や活発な議論を重視する少人数教育が実践されています。
実践的な学びと論文への応用
修士論文の執筆を通じて、理論だけでなく、現場での問題解決能力も磨かれます。明治大学専門職大学院では、学術的な議論に基づいた双方向授業を展開し、論理的に説明できる能力を養うことで、記述問題への対応力も高まることが期待されます。早稲田大学大学院では、ゼミ形式のワークショップ科目や論文執筆を行うテーマ研究科目を通じて、議論や文章化の能力を養うことができます。
専門的なライティング指導
論文執筆に必要な基礎スキルを体系的に学べるプログラムを提供する大学院もあります。LEC会計大学院では、税理士科目免除申請を想定した戦略的な修士論文指導体制を整えており、以下のような特徴があります。
- 毎週繰り返す草稿提出と指導のサイクル: 忙しい社会人でも時間を無駄にせず、確実に完成まで導く仕組みを整備しています。
- チーム制による指導: 主査となる指導教授の他に、構成指導と文章指導の担当教員が加わり、論理の一貫性や整合性、形式面・文章面での品質向上を目指します。
- アカデミックライティングの正規科目: 入学後最初の半期で、論文執筆のための基礎スキルを講義とグループワークを通じて習得する「アカデミック・ライティング」を正規科目として履修できます。
研究計画書の重要性
大学院の入試では、学力試験や面接と並んで研究計画書が選考基準となります。研究計画書は合否を大きく左右する重要な書類であり、自身の研究テーマや達成目標を具体的に記載し、それが税理士資格取得にどのように繋がるかを論理的に説明する必要があります。面接では、科目免除のための論文執筆が現実的に可能かどうかも重視される傾向にあります。
修士論文の審査は厳格化しているとの見解もあり、安易な免除は期待できないため、質の高い研究と論文作成が求められます。これらのサポート体制や自身の準備状況を考慮し、最適な大学院を選択することが、目標達成への鍵となるでしょう。
大学院入試の準備と選考で求められる要素
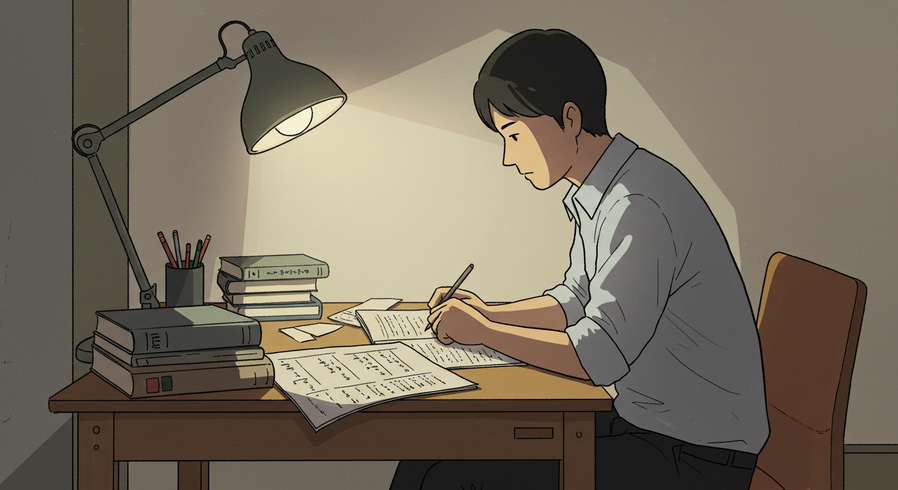
税理士資格取得を目指す上で大学院への進学を検討する際には、その入試準備と選考で求められる要素を深く理解しておくことが肝要です。大学院入試は、単なる学力だけでなく、自身の研究に対する意欲や将来のキャリアプランを明確に示す機会となるからです。
大学院入試の選考基準
大学院の入試では、一般的に学力試験、研究計画書、そして面接が主要な選考基準として挙げられます。学力試験では、経済学、経営学、会計学といった分野の基礎知識が問われることが多く、計画的な準備が求められます。面接では、学業やこれまでのキャリアにおける一貫性が重視される傾向にあり、将来の税理士としての展望についても整理しておく必要があります。特に、税理士試験の科目免除を目的とする場合、修士論文の執筆が現実的に可能かどうかという点が面接で重視される傾向にあります。
研究計画書作成のポイント
研究計画書は、大学院入試において合否を大きく左右する重要な書類です。自身の研究テーマと達成目標を具体的に記述し、その研究が税理士資格取得にどのように結びつくのかを論理的に説明する力が求められます。修士論文の作成を希望する学生に対しては、研究計画書も書類審査の対象となります。
入学前の準備とスケジュール管理
大学院入試に向けた準備は長期的な計画を立てることが成功の鍵となります。具体的には、各大学院の入試日程や必要書類を確認し、そこから逆算して準備を進めるスケジュールを作成することが効果的です。おおよそ、入試の約6か月前から研究計画書の作成や学力試験の対策を始めることが推奨されます。
入学前に準備すべき事項としては、以下の点が挙げられます。
- 入学条件と学費の確認: 進学を検討している大学院の入学条件や必要な学費を事前に詳しく調べる必要があります。学費が不足する場合は、入学までに貯蓄をしたり、奨学金制度の利用を検討し、事前の手配が必要です。
- 求められるスキルの学習: 入試で必要とされるスキルを学んでおくことが大切です。会計大学院の講義レベルは高く、日商簿記2級程度の知識ではついていくのが難しいとされるため、日商簿記1級レベルの知識を持っていることが望ましいとされています。日商簿記3級程度の知識から進学を考える場合は、まず日商簿記2級、さらには1級へと段階的に勉強を進めることが推奨されます。
- 意欲や資質: 「学ぶに足る意思」「的確な問題意識」「多量な予習に耐えられるタフさ」といった意欲や資質も重要視されます。
各大学院の入試における具体例
いくつかの大学院では、以下のような具体的な選考方法が採用されています。
- 東北大学会計大学院: 主要な入試区分として一般選抜と自己推薦入試があります。一般選抜では筆答試験(会計学)と口述試験が、自己推薦入試では書類選考と口述試験が行われます。
- 大原大学院大学: 一般入試では筆記および面接試験、自己推薦入試では書類審査や資格取得状況、面接試験により選考されます。
- 青山学院大学大学院: 書類審査と口述試験が課されます。口述試験では、簿記検定2級と3級で出題される商業簿記と工業簿記から問われ、口頭での説明が求められます。
- MARCHや関関同立の会計大学院: 税理士試験1科目合格程度の知識があれば院試に合格しやすい傾向があるとされ、日商簿記1級や税理士の簿記論・財務諸表論の合格が受験要件となる方式もあります。
入試自体の難易度は、公認会計士試験と比較して「そこまで難しいものではない」という見解もありますが、合格すれば「レベルが高すぎてついていけない」という心配はほとんどないとされています。
社会人学生のための追加の考慮事項
働きながら大学院への進学を考えている社会人の場合、特に以下の点が重要になります。
- 職場への相談: 会計大学院への入学は2年間の集中した学習を伴うため、本業に影響が出る可能性があります。職場に何も知らせずに入学すると、他の従業員に迷惑をかける可能性もあるため、事前に職場に相談することが大切です。
- 仕事・授業・プライベートの両立: 仕事、授業、そしてプライベートのバランスを保つことが、学習を継続する上で非常に重要です。無理なスケジュールはストレスの原因となり、授業にも影響を及ぼす可能性があるため、仕事量と必要な授業時間を考慮した上で、自身に合った無理のないスケジュールを立てる必要があります。
- スケジュール管理の徹底: 在職中の場合は、特にスケジュールの徹底管理が求められます。学習時間を確保するためには時間のやりくりが重要であり、例えば平日は通勤時間を利用して基礎学習を進め、週末はまとまった時間で研究計画書の作成や論文テーマの調査に充てるなどの工夫が有効です。具体的な進行状況をリスト化し、計画と照らし合わせながら修正を行うことで、効率的な準備が可能となります。
これらの準備と選考で求められる要素を理解し、自身の状況に合わせて戦略的に取り組むことが、大学院合格、ひいては税理士資格取得への重要な一歩となるでしょう。
大学院修了後の税理士としてのキャリア展望
税理士資格取得を目指す上で大学院への進学は、資格取得後のキャリア展望を大きく広げる可能性を秘めています。大学院で培われる高度な専門知識とスキルは、税理士としての実務において大きな強みとなり、多様なキャリアパスを築く上で有益です。
大学院修了者に求められるスキルと知識
大学院を修了した税理士には、税法や会計に関する体系的な知識に加えて、より幅広いスキルが求められます。例えば、クライアントとの効果的なコミュニケーション能力や、企業の事業戦略に対する深い理解は、税理士が専門性を発揮する上で不可欠です。
立正大学大学院の経営学研究科のように、会計学や経営戦略を深く学べるカリキュラムを持つ大学院では、税理士としての実務に直結する内容が提供されています。修士課程における修士論文の研究は、理論的な基礎を築き、資格取得後のキャリアに大きな影響を与える可能性があります。また、会計大学院では、実務家教員が教鞭を執ることが多く、実務に即したカリキュラムを通じて、実務で活用できる知識やスキルを身につけることができます。
税理士事務所での課題とキャリア拡大の道
税理士事務所の業務は、従来の中小企業の決算や申告に加えて、近年では事業承継、M&A、国際税務といった専門性の高い分野での需要が増加しています。大学院での研究や修士論文を通じてこれらの専門知識を深めることは、事務所が直面する多様な課題に対応するための大きな強みとなります。
例えば、甲南大学大学院社会科学研究科で学べる租税法や経営学の知識は、税理士業務の枠を超えた幅広いニーズに対応する素養を養う上で適しており、顧客層の拡大や高単価案件の獲得にも繋がる可能性があります。さらに、会計大学院では、国際会計基準(IFRS)を学べる機会も多く、これは海外進出を目指す税理士にとって推奨される学習となります。大学院での学習は、独学や予備校での学習と比較して、実務家を養成する目的があるため、より体系的な知識と幅広いノウハウが得られ、キャリアアップに差が出る傾向があります。
将来を見据えた大学院選びの重要性
税理士資格取得後のキャリアを充実させるためには、進学する大学院の選択が極めて重要です。単に税理士試験の科目免除制度の有無だけでなく、提供されるカリキュラム、税法担当教授の専門性、卒業後のキャリアサポート体制なども重要な選定ポイントとなります。ランキング上位の大学院は、一般的に学習環境が整備されており、優れた研究内容や業界内でのネットワーク構築が期待できます。
大学院の教員や、官公庁や大手企業に在籍する社会人学生との交流を通じて、将来のための人脈を築く機会も得られます。このようなネットワークは、公認会計士や税理士にとって貴重な財産となり、その後のキャリアにおいて有利に働くことがあります。
オンライン講座や働きながら学べる制度の活用
近年、多忙な社会人でも大学院進学が現実的な選択肢となるよう、オンライン講座や働きながら通える制度が充実しています。例えば、一部の大学院では夜間開講やオンライン授業を導入しており、キャリアを中断することなく資格取得を目指したい方にとって、こうした柔軟な学習環境は非常に適しています。
LEC東京リーガルマインド大学院大学のように、すべてのコースをオンラインのみで完結できる大学院も存在し、日本全国から海外在住の社会人までが学んでいます。このような大学院では、オンラインライブ授業やクラウドでの情報共有、オフィスアワーや懇親会を通じたコミュニケーションサポートも提供されています。また、修士課程の学費補助や奨学金制度を活用することで、金銭的な負担を軽減し、学習を継続することも可能です。自身のスケジュールや経済状況に合わせて、多様な学び方を検討することが、税理士としてのスキルアップへの近道となるでしょう。
実務で活かせる知識・スキルと人脈形成

大学院での学びは、税理士としての実務に直結する高度な知識やスキルを習得し、同時に将来のキャリア形成に不可欠な人脈を築く貴重な機会を提供します。
実務に直結する知識と専門性の深化
大学院を修了した税理士には、税法や会計に関する体系的な知識に加えて、より幅広いスキルが求められます。単に資格試験の合格に留まらず、実務で活用できる知識やスキルを身につけることが重視されます。
多岐にわたる専門分野への対応
具体的には、多岐にわたる専門分野への対応能力が大学院で培われます。従来の決算や申告業務に加え、近年増加している事業承継、M&A、国際税務といった専門性の高い分野への需要に対し、大学院での研究がこれらの課題に対応する上で大きな強みとなります。また、国際会計基準(IFRS)を学べる機会も多く、海外進出を目指す人にとっても推奨される学習となります。
網羅的な税法科目
網羅的な税法科目の例としては、熊本学園大学大学院会計専門職研究科が挙げられます。ここでは、総論としての租税法原理だけでなく、法人税、所得税、消費税、相続税など個別の税法科目も網羅的に開講されています。
実務に即した教育と応用力
実務に即した教育と応用力も大学院の大きな特徴です。多くの会計大学院では、現役で活躍する公認会計士や税理士が教員を務めており、実務に即したカリキュラムを通じて、実務で活用できる知識やスキルを身につけることができます。非会計分野の知識も習得可能です。立正大学大学院経営学研究科のように会計学や経営戦略を深く学べる大学院や、関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科のようにビジネススクールの科目も履修できる大学院では、マーケティングや情報システム学、経済学、統計学、ITといった会計隣接領域の知識も習得でき、幅広い視点から企業経営を理解する素養が養われます。実践的な問題解決能力も磨かれます。論文執筆や演習を通じて、法的思考、文章作成能力、ディスカッションの進め方が向上し、理論だけでなく現場での問題解決力が磨かれます。北海道大学大学院経済学院では、講義形式だけでなく、学生同士の活発な議論や「唯一の正解のない問題」に対する多様な解決策を導き出す能力の涵養に重点が置かれています。これにより、経験則や感覚に頼らず、理論的に整理し、根拠ある判断や説得力のある提案ができるようになります。
貴重な人脈の形成とキャリアへの影響
大学院は、高度な専門知識の習得に加え、将来のキャリアに大きな影響を与える人脈を形成する貴重な機会を提供します。
多様なバックグラウンドを持つ学生との交流
多様なバックグラウンドを持つ学生との交流もその一つです。社会人向けコースには、会計の実務家だけでなく、弁護士や官公庁、大手企業に在籍する社会人学生など、多種多様な経歴を持つ人々が集まります。こうした学生間のネットワークは、情報交換や相互の切磋琢磨の場となり、将来的に仕事の相談相手や貴重な財産となり得ます。
教員との連携
教員との連携も重要です。会計業界で活躍する教員や試験委員経験者と交流することで、出題の理念や傾向に触れる機会も得られ、彼らからの指導やサポートは論文執筆やキャリア形成において大きな助けとなります。
同窓会組織の活用
同窓会組織の活用もキャリア形成に寄与します。関西学院大学の“弦月CPA会”や熊本学園大学の「志文会」のように、卒業生組織が学生や修了生のキャリアをバックアップし、情報交換や就業体験の機会を提供する大学院もあります。
このような人脈や、独学では得られない幅広い知識・ノウハウは、就職後のキャリアアップに差が出る傾向があると言われています。大学院での学びは、公認会計士にならなくても、さまざまな業種業界、職種で活かせ、将来のキャリアの可能性を広げることができます。
会計大学院進学における主な注意点
会計大学院への進学を検討する際には、多岐にわたる側面からの慎重な検討が不可欠です。単なる科目免除の有無だけでなく、自身のキャリア目標や学習スタイルに合致するかどうかを見極める必要があります。
学費と時間的投資
大学院進学は、学費や時間の面で「非常に大きな投資」となります。多くの場合、2年間の修士課程を修了する必要があり、年間100万円以上、私立では年間150万円以上の学費がかかる大学院もあります。2年間の合計学費は、国立で130万円以上、私学で350万円以上となるケースも指摘されています。働きながらの進学の場合、学費の高さに加え、正社員を辞めると収入が途絶えるか激減するため、資格取得に失敗した場合の経済的リスクが大きいとされます。また、卒業までに2年間を要するため、社会に出るのが遅れることで選択肢が狭まる可能性も指摘されています。
学習内容と難易度
会計大学院の学習レベルは高く、日商簿記2級程度の知識では授業についていくのが難しい可能性があります。在学生の多くは日商簿記1級を半分の時間で「楽勝」と感じる程度の知識を持っていると評されています。入学試験や定期試験は論述形式が多く、扱う内容もかなり難しい傾向にあります。大学院の授業は、公認会計士試験の受験対策に直接的にならない場合が多く、多くの学生が専門学校とのダブルスクールを必要としているのが実情です。大学院の授業や論文執筆が、かえって試験勉強の負担になることも指摘されています。
科目免除制度の理解
税理士試験の科目免除を目指す場合、修士論文の指導ができる教授がいる大学院を選ぶ必要があり、同じ大学院内でも研究科によって指導可否が異なるため、事前の確認が不可欠です。また、会計大学院在学中は、一般の受験者と同様に全科目の合格が必要であり、免除される科目は修士論文の審査が認定されることが条件です。かつては「確実に免除を取れる」と謳う大学院があったとしても、現在は論文審査が厳しくなっており、安易な免除は期待できないという見解もあります。
大学院選びのポイント
進学予定の大学院が税理士試験の科目免除制度に対応しているか、提供されるカリキュラム、税法担当教授の専門性、卒業後のキャリアサポート体制などを確認することが重要です。また、自宅からの通学のしやすさ、オンライン講座や夜間開講の有無も考慮すべきです。ランキングは有益な情報源となりますが、一定の主観が含まれるため、自身の目標や生活スタイルと比較しながら検討することが大切です。国立大学院の中には、資格試験のための科目免除に対して理解がない教授が多い傾向があるという意見も存在します。
入学前の準備と両立
大学院入試や進学準備は長期的な計画(約6ヶ月前から)を立てることが成功の鍵です。特に社会人の場合、キャリアを中断せずに資格取得を目指すためには、仕事、授業、プライベートを両立させるスケジュール管理が極めて重要です。入学前に職場に相談し、理解を得ておくことも推奨されます。
会計大学院どこがいい?おすすめ大学院と選択基準:まとめ
記事のポイントをまとめます。
- 税理士になるための会計大学院選びは科目免除制度の活用が大きな利点
- 税法や会計の修士論文提出で税理士試験の科目免除が可能となる
- 社会人向けのオンライン完結や夜間・週末開講の大学院も多数存在する
- LEC会計大学院はオンライン完結で社会人向けカリキュラムが充実
- 大原大学院大学は資格対策講座との連携が強みである
- 千葉商科大学はオンライン授業と専門実践教育訓練給付金に対応している
- 武蔵野大学は予備校提携と奨学金制度が手厚い
- 会計大学院進学は学費が高額になる経済的負担も考慮すべきである
- 2年間の修了期間はキャリアの空白期間となり得るデメリットがある
- 大学院の授業だけでは試験対策が不十分でダブルスクールが必要な場合がある
- 公認会計士試験の免除は短答式試験の一部に限られる点に注意が必要である
- 税理士試験の論文審査は厳格化しており安易な免除は期待できない
- 科目免除での資格取得は就職時に評価が低いとされるケースがある
- 論文指導や少人数教育、実務家教員の有無が大学院選びの重要ポイントである
- 大学院での人脈形成や幅広い知識習得は長期的なキャリア形成に役立つ